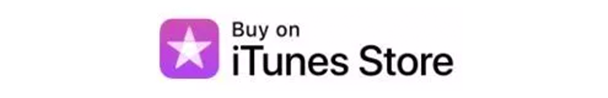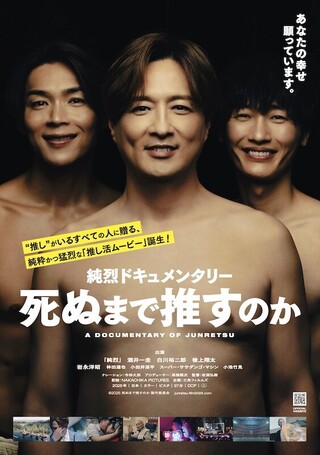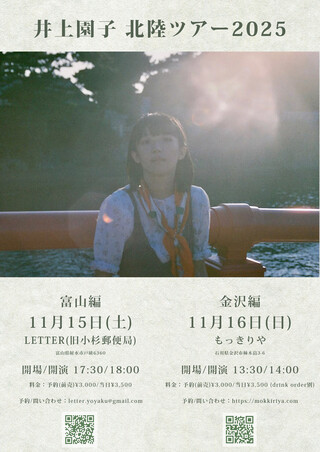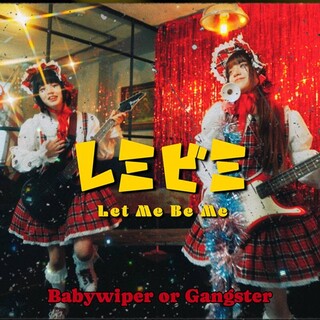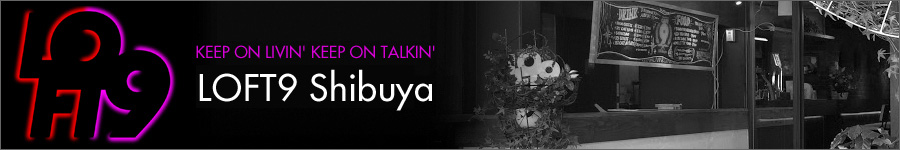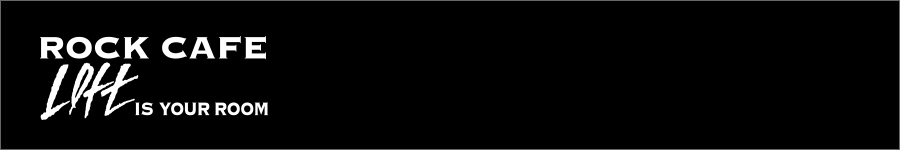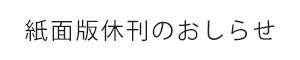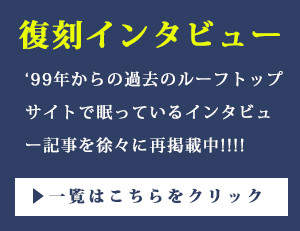ジブリ映画への愛情〜男の子が自分の限界を超えてがんばる、その瞬間に生まれる気持ちよさ〜アジアからヨーロッパを駆け抜けていくような無国籍メロディ〜スクエアプッシャー、エイフィックス・ツインに代表される先鋭的エレクトロミュージック〜目の前にいるオーディエンスを躍らせることの楽しさ〜意味もなく、ワクワクしてくるような高揚感〜聖蹟桜ヶ丘駅から多摩ニュータウンあたりの風景。
DE DE MOUSEの2年ぶりのニューアルバム『A journey to freedom』には、彼自身の好きなもの、やりたいこと、美意識、価値観が濃密に反映されている。圧倒的な情報量の多さ、ダンスミュージックとしての高い機能、そして、ノスタルジックかつアッパーな旋律。DE DE MOUSEの個性を炸裂させるとともに、あらゆるタイプの音楽ファンを興奮させる、驚異的なアルバムの誕生である。(interview:森 朋之)
メロディに反応して高揚してくれるものを
──約2年ぶりのフルアルバムということですが。
「はい。丸2年ぶりですね」
──この2年間、「DE DE MOUSE」の名前をいろんなところで見聞きするようになったわけですが、ご自身の実感としてはどうですか?
「まあ、ライブ活動がメインになってましたからね。メジャーに来る前から大体、週1回くらいはライブをやってたんですよ。昨年はそれよりちょっと多くて、60本くらいだったのかな? でも、自分のなかではそんなに変わったっていう感じはないんです。フジロックとかに出るようになって、そのぶん、目にしてもらえる機会が増えただけじゃないかなって思ってますけどね」
──認知度が上がってる気もしない?
「どうかな? まあ、それまでずっとひとりでやってたのが、バンド編成になったりしましたからね。クラブだけじゃなくてロックのフィールドにも"DE DE MOUSE っていうヘンなのがいるぞ"って呼ばれるようになったりして──キワモノ的な扱いだと思いますけど──それまで知らなかった人たちにも見せられるようになった、っていうのはあるかもしれない。そこは変わったといえば変わったのかな。あと、どうにもこうにもならないようなコメント撮りとかね、そういうどうしようもない稼動はたくさんありましたけど。"制作に集中させろよ!"みたいなこともありつつ(笑)。avexに来る前に比べたら、確かに忙しくはなってますね」
──制作に集中したいっていうのは、本音ですよね?
「そうですね。僕を家から出すなよ! って(笑)。そういうことだけじゃなくて、私生活でもけっこう激変だったりして──顔つきがぜんぜん違いますからね、2年前とは。avexに来たばかりの頃は子供っぽかった。考え方でも何でも子供っぽかったしね、実際。メジャーっていうものに期待や希望を持っていたんだけど、まわりの人たちに丸め込まれることもあり」
──オトナになってしまった、みたいな。
「いい意味でも、悪い意味でも(笑)」
──でも、今回のアルバムは素晴らしいと思いますけどね。すごく高揚したし、思い切り楽しませてもらいました。
「ありがとうございます」
──とにかく情報量の多いアルバムですよね。
「これでもかなり整理したんですけどね。次はさらにとんでもないことになると思います」
──表現したいことが膨大にあった、という気がしたんですよね。
「そうですね。前作の『sunset girls』は、かなり削ぎ落としたアルバムだったんですよ、自分のなかで」
──え、そうですか? 十分カラフルだと思ったんですが。
「最初はもっと地味だったんです。1st(『tide of stars』)のときは"クラブシーンでも、もっとメロディを聴かせたい"っていうのがあったんですよね。誰とは言いませんけど、ピアノハウスみたいなものが30万枚くらい売れたりしていて、そういうものが好きじゃなかったんです。それとは違うカタチで、みんながメロディに反応してワーッとなってくれるものを作ってみたいっていう。そういう音楽がアンダーグラウンドで盛り上がったらいいだろうなって思ったんですよね」
──なるほど。
「で、実際にクラブでプレイすると、ちゃんとみんな反応してくれたんですよね。1stは自分の予想以上に反響があったし。ただ、そうなると自分のなかでは他人事なんですけどね。レーベルオーナーから"こんなに売れてるよ"って聞かされても、"あ、すごいっすね"みたいな(笑)」
──次の作品に向いてた、ということですか?
「そうですね。自分としては、さらにメロディを強く押し出したアルバムを作りたかったんです。そのころのクラブ・シーンはダブステップとかが流行ってたんですけど、それは自分の好みではなかったし、ダンスミュージックとは違うものばかり聴いてましたからね。80年代のフュージョンだったり、前から好きだったキリンジだったり、あとは『となりトトロ』だったり。とにかく、"もっと日本っぽくするには、どうしたらいいだろう"って、そればっかり考えてた。ちょうどインディーズからメジャーに移るタイミングだったし、クラブのシーンとはちょっと距離がありましたね」
次の橋渡しになるアルバム
──その結果『sunset girls』は、余計な音を削ぎ落として、メロディを強調した作品になった、と。
「さっきも言いましたけど、初めはもっと地味だったんです。2007年の秋に入院しちゃったんですけど、退院してから聴いてみたら"いくらなんでも地味すぎるだろう"って思って、そこからちょっとアレンジをやり直して。完成度の高い作品になったと思うし、あんなに複雑なコード感のアルバムをavexから出すっていうのも、おもしろいんじゃないかなって...。まあ、あのときもいろいろありましたけどね。"少女がお祭りに行く"っていう物語を設定してたから、それを映像化したらおもしろいだろうな、とか、自分たちが演奏している後ろで、影絵のショーみたいなものが出来たらいいな、とか考えてたんですけど、そこでもスタッフの口八丁に丸め込まれて」
──(笑)やりたいことが出来なかった。
「バンドで演奏したいと思って"ドラムを入れたい"って言ったら、"じゃあ、君がいいと思うドラマーを探して、ギャラを聞いて"って。え、俺がやるの? ってケンカしたりケンカしたりケンカしたり...」
──タフにならざるを得ないですねえ。
「海外でライブしたり。昨年60本くらいライブやったって言いましたけど、毎回フロアがギューギューかっていえば、そうじゃないですからね。フタを開けてみると客が3人しかいなかったこともあるし、そこでどう見せるか? っていう覚悟も決まったし。2ndを作ってたときは周りをシャットアウトしてたところがあるんだけど、ライブをやっていくなかで、みんなを躍らせるのは楽しいなって思うようになってきたんですよね。一番大きかったのは、"TAICOCLUB"っていう長野でやってるイベントで、スクエアプッシャーが出てたことなんですよ。ホントにもう、自分がこういう音楽をやるきっかけになった人だし、"自分のライブなんかどうでもいい"ってくらいに楽しんで。で、ほんっとに感動して」
──どんな感じだったんですか、今のスクエアプッシャーは。
「一時期、スピリチュアルな方向に行っていて、メロディアスなものは全然やらなくなってたんですよ。2001年くらいのフジロックに来たときは、それが一番顕著だったときで。だけど昨年見たときは、"こんなにサービスする人なんだ!"ってくらい、初期の名曲をどんどんやってたんですよ。僕の好きな曲、全部やってくれた! くらいの。何ていうか、客が求めてることがわかってても、"俺はそんなのやらない"っていう人だと思ってたんですよ。でも、それはメディアが勝手に作り上げたイメージだったんだなって。たぶん、もっと自由にやってるんですよね。そのことを体で感じたことで、僕自身も肩の荷を降ろせた気がしたんです。やっぱり、やりたいことをやろうって」
──なるほど。
「スクエアプッシャーとかエイフェックス・ツインとか、情報量の多いエレクトロミュージックはやっぱり好きなんですよね。2ndを作ってたころは、そのあたりはもう引退しようと思ってたんです。自分にはそっちの才能がない、と思ってたから。でも、やっぱり捨てきれないないし、好きだし、かっこいいし。あと、みんながイメージするDE DE MOUSEって、1stだと思うんですよね。だから今回は、今の僕から見たDE DE MOUSEをやってみようと思ったところもあって。そうやっていろんな距離感を取りつつ、1年半くらいずっと作ってましたね。何度もアレンジをやり直したり、バランスを取るのは大変だったんですけど」
──今回のアルバムの曲って、リズムがクルクル変化していくじゃないですか。今の話を聞いて、その理由がわかったような気がしました。
「わかりやすいですからね(笑)。ただ、今言ったみたいに"もっと自由に表現したい"っていうのはすごく感じてて。距離感やバランスもちゃんと考えるけど、根本は好きなことをやる。それができないんだったら、avexをやめてやる! みたいな気持ちがすごく芽生えてて。スタッフ的に"もっとこうしてほしい"っていうもあったと思うんだけど、僕がガンコで言うこと聞かないっていうのも知ってるだろうし、最後はサジを投げてましたけどね、"好きにしろ"って。僕のほうも、最終的にはみんなに納得してもらえるものにするっていうポリシーとモットーでやってるし。これもやりたい、あれも聴いてほしいってやってると、どうしてもゴチャゴチャになっちゃう。だから今回は、"この曲ではこれ、こっちはこれ"っていう感じで整理していったんですよね。そういう意味でも、次の橋渡しになるアルバムになったんじゃないかなって」

pic by manabu numata