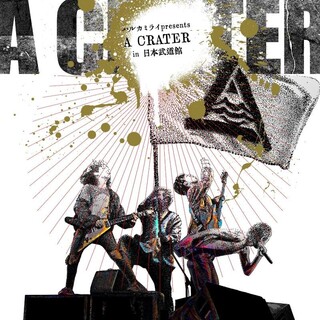拝啓、キング・オブ・ロックンロール。そっちの調子はどうですか。サム・クックやオーティス・レディングと賑やかにセッションしてますか。あなたの訃報を聞いてから早ひと月、心にポッカリと開いた穴が未だに塞がりません。ポップでありながら反骨であり続けることの大切さをあなたから教わりました。そんなささやかな信条を胸に秘めて僕はこれからもしがない編集稼業に身を投じていきます。その信条とあなたの歌がある限り、あなたの生は今なお激しく脈打ちながら息づいているのです。僕は僕なりの弔いとして、あなたが唯一本誌の表紙を飾ってくれた号のインタビューをここに再掲載します。ありがとう、キヨシロー。そしてこれからもよろしく。(text:椎名宗之)
旅することが目的だった
ロックは実にたくさんのことを教えてくれたが、とりわけ"自由に生きるとはどういうことか"を教わったと思う。私が音楽を聴き始めた頃、最もぶっとんだロックを聴かせてくれたのが忌野清志郎のRCサクセションであった。そして彼は今現在もラフィータフィーでいかしたロックをやり続けている。そう、日本において忌野清志郎ほど"自由"を感じさせてくれるロックンローラーは他にいないのではないだろうか。全国を回るライヴハウス・ツアー『マジカデ・ミル・スター・ツアー』が今年はなんと新宿ロフトにやって来るという。最高のロックンロール・バンドを体感するまたとないチャンス! ロックの神様、ありがとう!(interview:加藤梅造)
単純に音楽を聴かせるっていうのがいい
──清志郎さんは常々、自分はミュージシャンじゃなくてバンドマンだって仰ってますが、これだけのキャリアを積んでもなおバンドにこだわるっていうのも珍しいですよね。
忌野:そうですよね。でもなかなかバンドとして認めてもらえないんですよ。どうしても忌野清志郎って名前が出てしまって。それがちょっとジレンマなんですね。
──RC休止後は、ソロ・アルバムも結構出してましたよね。
忌野:でもやってくうちに、だんだんバンドになってっちゃうんですね。自分の昔の曲をやるんでもね、その通りにはできないって言うか、その時組んでるバンド流にアレンジしないとしっくり来ないんです。
──ラフィータフィーを作った感じっていうのは、RCを作った時と同じ感じなんでしょうか?
忌野:うん、似てますよ。なんか張りが出るっつうか。
──映画(『不確かなメロディー』)の中でもされてた質問ですが、なんでバンドにこだわるんですか?
忌野:なんでだろうね。まぁイメージ的な部分も大きいんですけど、ソロ・シンガーだとバックは誰でもいいわけじゃないですか? 譜面さえ渡せば。
──ラフィータフィーはパーマネントなバンドと考えていいんですよね。
忌野:もちろんそうです。
──ファンとしては、またライヴハウス・ツアーを観れるのが凄く嬉しいんですが、昨年の秋に続いて3度目のライヴハウス・ツアーですよね。やっぱり面白いですか?
忌野:そうっすねぇ。面白いっすね。
──最初は不安もあった?
忌野:どうなることやらって。ライヴハウス・ツアーっていうのは、ほとんど何年ぶりでしょうねぇ。20年ぶりぐらいかなぁ。
──20年前と言うと、ライヴハウスも今とは随分違うんでしょうね。
忌野:全然違いましたね。数も少ないし。そう言えば、なんか凄い所ありましたよ。狭いステージでバンドのメンバーが僕のすぐ後ろにいたんだけど、最後のほうでノってきたら、僕とメンバーの間に客がいるんですよ。それでバンドも客も関係なく一緒になって盛り上がってましたよ(笑)。
──これぞライヴハウスって感じですね。ところで、ライヴハウス・ツアーをやろうと思ったきっかけって何だったんですか?
忌野:何かねぇ...。ロリータ18号の『アメリカ珍道中』っていうビデオを見たんですよ。ライトバンみたいなのでアメリカ中を回って、自分達で物販したり、地元のラジオ局に出たりするビデオなんだけど、それ見て羨ましいなぁって思っちゃったんですよ。で、日本でも同じことやってるって聞いて、じゃあ俺達にもできないことはないんじゃないかなって。
──確かにできないことはないですよね。
忌野:やればいいのにね、みんなも。
──日本においてRCサクセションが武道館でライヴをやるということを確立し、今ではドームでさえ当たり前のようになっている状況があると思うんですが、今また清志郎さんがライヴハウス・ツアーをやるというのが実に新鮮だと思うんです。
忌野:なんかねぇ、ホール・ツアーってひとつのショーになっちゃってる気がしてきたんですよ。照明や音響などのスタッフがたくさんいたりとか。ライヴハウスってそういうのあんまり関係ないじゃない? 単純に音楽を聴かせるっていうのが、なんかいいなぁと。友達の家のパーティーで演奏してる感じですね。
──考えてみれば、清志郎さんって日本のロックの黎明期を知ってる人だから、ライヴハウスってものを一番よくわかってるわけですよね。
忌野:僕らが始めた頃はライヴハウスって言葉すらなかったですから。ジャズ喫茶とかフォーク喫茶とかそういう時代でしたね。
初めての飛行機とホテル
──僕が映画を見て一番感じたのは、ああ旅をしてるなってことだったんです。
忌野:まさにそうですね。旅することが目的だったから。
──昔から旅が好きなんですか?
忌野:好きみたいだね。デビュー当時ツアーに出て、何が感動したかって言うと、初めて飛行機に乗ったのと(笑)、初めてホテルというものに泊まったらビックリしたんですよ。自分ちよりも良くて。銀のお盆とかコーヒーカップとかあって、おまけに風呂まで付いてる。こっちのほうがいい暮らしできるじゃねぇかって(笑)。
──『よそ者』って曲(『BLUE』収録)があるじゃないですか。清志郎さんが旅をしてる時の心情ってやっぱりああいう感じなのかなって。知らない場所でよそ者になるのが好きなんでしょうか?
忌野:好きかもしんないですねぇ。特にあの曲を作った頃はロック・バンドというもの自体がよそ者扱いだったんです。テレビの歌番組に出ても、他の人はほとんど歌謡曲や演歌で「ああ、俺達よそ者だな」って思ったんですよね。
──なるほど。そう考えると、清志郎さんってどこへ行ってもよそ者的な感覚を持っているような気もしますが。
忌野:そうですかねぇ?
──基本的にロック・ミュージシャンって社会にとってはよそ者みたいなもんだと思うんですが、売れると丸くなっちゃう人もいると思うんです。
忌野:たぶん、ミュージシャンだけじゃなくて誰でも若い時は、自分の力で何か変えてやろうという気持ちで始めたと思うんですよ。たとえば、レコード会社の今のシステムを変えてやろうとか。でもだんだん成功するにつれ、どんどん体制側に取り込まれていくっつーか、普通になっちゃって。で、今度は何か新しいものに対して、昔自分がやられたようなことをやってるっていう。これが不思議ですよね。
希望は捨てない
──あと、映画の中で印象的だったのが"夢"の話をする場面だったんです。そこで清志郎さんは「俺の夢は世界中から戦争がなくなること」って言ってるんですが、あまりにストレートすぎて僕は凄く感動したんです。普通なかなか言えないですよ。
忌野:うーん...言いたいんですよ、なんか(笑)。いい大人がね、本気でそう思ってるんだっていうことを言っとかないとなっていう。
──たとえばジョン・レノンが"WAR IS OVER"って言った頃はヴェトナム戦争とかあって社会全体に反戦ムードがあったと思うんです。でも今の時代はむしろ平和ボケとか言われてて"LOVE & PEACE"が説得力を失ってますよね。
忌野:本当は若い頃も言いたかったんですよ。でも、あんまり若いのにそういうこと言っても説得力ないじゃないですか。何言ってんだみたいな。でも今の歳になってもその気持ちは変わってないので、まぁ思ってるんだったら言っとこうかなって感じなんですよね。戦争について言うと、なんか議論が盛んになってく中で言葉だけがすり替わって、結局、自民党とかは海外派兵に持ってきたいわけじゃないですか。軍隊作ったり。それが今の先進国の考えみたいになってるけど、僕は全く違う考え方でいいと思うんですよね。ちゃんと説明できれば。
──原発にしても、何となくうやむやにされている感じがありますよね。最近のコマーシャルとか見てると、水力発電や風力発電と原発を無理矢理結びつけてクリーンなエネルギーでございます、みたいな詭弁を平気でしてるじゃないですか。
忌野:そうなんですよね。僕の知り合いのカメラマンでね、日本の原発を全部撮って写真集を出してる人がいるんですけど、凄いですよ、もう。僕が『COVERS』出した頃は、日本の海岸に47基ぐらい原発があったんですよ。それが今(2001年)は60基に増えてるんです[註:2009年5月現在、日本では全53基中31基の原子力発電所が運転中]。海岸の凄い風光明媚でめったに人の来ない所に隠れて建ってるんですけど、その建物の耐用年数がたったの30年なんですよ(笑)。
──そういう話を聞くと、こりゃもうダメかなとも思ってしまいますよね。『口癖』(『秋の十字架』収録)でも"バカなんじゃない人類って"という歌詞がありますが、清志郎さんの中にはそういったある種の諦めと、でも何とかしなきゃという思いの両方があるんですか?
忌野:でも僕は希望は捨ててないんですよね。と言うのは、子供の頃、国立に多摩川って川がありまして、よく釣りに行ってたんですけど、いっぱい釣れたんですよ。それがね、僕が高校生ぐらいになったらちょうど高度成長で、工場が汚水を多摩川に捨て出したんですよね。それである時期から見る影もなくなってヘドロの川になっちまったんです。その後、石油ショックとかいろいろあって、みんなヘドロはいかんって気がついたんでしょうね。それでやっと次第に魚が戻ってきたんですが、ずっとその様子を目の当たりにしてきたんです。人間って本当に身体でもヤバくならないと医者行かないじゃないですか。病気に気がつかないと言うか。そういうことだと思うんです。いつか気がついて、やっぱり元に戻そうっていうことになるんじゃないかなっていう希望はちょっと持ってるんです。
最後は、一人一人が真面目になんなきゃ
──『グレイトフル・モンスター』(『秋の十字架』収録)では、子供達の置かれている不安な状況を唄ってますが、子供に対する大人の責任っていうのをどう意識してますか。
忌野:うーん、大人がやっぱりもっと真面目になんないとダメだと思うんです。真剣に生きるっつーかねぇ。いい加減な大人が増えたんじゃないですかね。子供から見て大人が怖くもないし、尊敬もできないっていう。
──やっぱり今の状況じゃまずいと思います?
忌野:しょうがないですよねぇ。政治家もダメだし、警察もダメだし...きっと、国が弱まってきてるんでしょうね。雪印の事件にしても、昔は牛乳飲んでりゃ絶対大丈夫だったじゃないですか。そういうのが壊れてきて、今レコード会社もそうでしょ。
──人間弱くなると誰かにすがりたくなるじゃないですか。たとえば石原都知事が支持される背景ってそういう理由だと思うんですよ。
忌野:そう、政治に反対するデモもなくなりゃあ、メーデーもなくなって、何にもなくなっちゃうわけじゃない、反抗するパワーが。石原慎太郎が持て囃されてるけど、結局彼は軍隊作りたいだけじゃない? 軍の力でみんなを引き締めて国を強くしようという考え方でしょ。うーん、どうしたらいいんですかねぇ。最後は、一人一人が真面目になんなきゃダメだと思うんですよ。何やるんでもね。
──随分前に読んだんですが、『十年ゴム消し』(忌野清志郎・著)に書いてある"どうせ ぼくは負けてしまったように見えてしまうのさ 口の達者な奴こそ英雄さ"という言葉が凄く印象的だったんです。で、非常に失礼な言い方なんですが、もしかして清志郎さんは、未だに負け戦かもしれない戦いをしてるんじゃないかなって思ってしまうんです。
忌野:ああ、そうですねぇ(笑)。そう言えばそうかもしれない......それでもやっぱり、戦わないよりはよっぽど素晴らしいと思いますよ。
※本稿は、本誌2001年6月号に掲載されたインタビューを再構成したものです。